情報用紙の品種説明
以下に、代表的な品種について順に説明していきます。
1.複写原紙
コンピューターのアウトプットに使用される用紙で特殊な薬品を塗工したものであり、ノーカーボン原紙、裏カーボン原紙、その他複写原紙があります。
(1)ノーカーボン原紙
ノーカーボン紙は感圧複写紙といわれ、筆圧、タイプライター等、機械的または衝撃的圧力によって発色し、同時に複数枚の複写を取ることのできる複写紙です。転移タイプと単体発色紙があります。
書き写しを取るために紙の間に挟んで使う色付きの艶の紙をカーボン紙(カーボンペーパー)といいます。カーボン紙はカーボンインクと呼ばれる特殊な複写用インクを原紙の裏面に塗布することで複写が可能であるのに対し、ノーカーボン紙はそのカーボン紙を使わずに、一番上の紙にペンなどで書き込めば、その下に重ねた数枚の紙にも書き写せます。このようにカーボンインクを塗布していないために「ノーカーボン」という名称がついているわけです。そのためノーカーボン紙のことを英語では、カーボンレス・コピー・ペーパー(Carbonless Copy Paper、略称CCP)といいます。
ノーカーボン原紙は、ノーカーボン紙の基紙となるもので、複写原紙の代表格です。ノーカーボン紙は1954年に米国・NCR社で開発され、わが国では1962年に生産を開始しました。化学的感圧紙とか、NCR紙とも呼ばれています。
従来、複写のためにはカーボン紙が広く使用されていましたが、手を汚したり、使い勝手が悪いといった点から、紙自体に複写機能を持つノーカーボン紙が開発されたわけです。カーボン紙なしで複写が取れるので、利便性がよく大きく成長しました。ノーカーボン紙の用途は事務分野の帳票、単票のほか、コンピーターアウトプット用の連続伝票などにも広く使われています。
その発色機構は不揮発性溶剤にロイコ色素を溶解して、これをメラミン、ポリウレア、ポリウレタン、ゼラチンなどの高分子皮膜で包んだ大きさ10~15μmと極めて小さいマイクロカプセルを塗布した上用紙と、電子受容性顕色剤を微粒子とし、顔料、バインダーとともに塗布した下用紙とを、その両塗布面を対向させた後、筆圧などによりマイクロカプセルを破壊して、ロイコ色素溶液を留出させ、顕色剤と接触させることにより発色させるものです。ここで図1にノーカーボン紙の発色原理図(複写伝票・ノーカーボン紙 [米村印刷WEBサイト]から引用)を示します。
図1.ノーカーボン紙の発色原理(模式図)
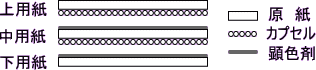
複写枚数に限らず、1番上には「上用紙」(一番上の紙)、中間は「中用紙」(間に挟まれる紙)、一番下には「下用紙」(一番下の紙)を使用します。通常は上用紙、中用紙および下用紙の3種類で構成されており、3枚1組の組み合わせて使用されます。上用紙と中用紙の裏面には不揮発性オイルに溶解した無色の色素(ロイコ染料)を封入したマイクロカプセル(発色基材、発色剤)を塗布、さらに中用紙と下用紙の表面には、上記色素を発色させるために酸性物質であるサリチル酸系などの顕色剤が塗布してあります。
各シートを図1のように重ねて上用紙の表面に、筆圧や印字圧、すなわち通常、ボールペンなどで記入するか、プリンターのインパクトにより印字します。この印字時の圧力で、上・中用紙のマイクロカプセルが壊れ、カプセル内の色素(無色染料)が紙表面の顕色剤と瞬間的に化学反応を起こして発色し表面に文字・画像を形成、複写される仕組みになっています。標準坪量は40g/m2、発色は青、黒が主流ですが、赤や緑などもあります。
以前はマイクロカプセルのオイルに、有毒なPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用されていましたが、すべて回収され1972年には製造中止となりました。
また、原紙の同一面に中用紙の両方の成分に相当するマイクロカプセルと顕色剤が塗工されているセルフコンティンド紙(セルコンペーパー=単体発色紙)または自己発色感圧記録シートがあります。これは一枚で発色が得られるため塗工面をラミネート加工し、親展はがきなどに使用されています。
今後、成熟商品化しているノーカーボン紙の大きな伸びは期待できませんが、光学的文字読み取り(OCR)用途や、ノンインパクト(NIP)方式である高速レーザープリンターなどでのカット判対応紙や、再生ノーカーボン紙などの上市が行われています。
なお塗布してある薬品が古紙リサイクル工程で化学反応を起こし、できあがった古紙の品質を悪くしてしまいますので、一般の用紙と混ぜての古紙再生ができません。そのため「古紙標準品質規格」でカーボン紙やノーカーボン紙などは禁忌品とされており、一般紙との混用は禁じられています。
注記
カーボンペーパー(carbon paper)が「和紙ベース」で作られていたということです。主として蝋および油を適当に混合し、これに油煙・紺青(こんじょう、青色顔料の一。ヘキサシアノ鉄Ⅱ 酸塩(フェロシアン化物)の溶液に硫酸鉄Ⅱ を加えてできる白色沈殿を、塩素酸ナトリウムで酸化して製する。印刷インク・絵具・塗料などに用いる)または有機性のレーキ(水溶性の染料に金属塩などの沈殿剤を加えて不溶性にした有機顔料。印刷インク・絵具・着色剤などに用いる。lake)などを配合し、雁皮紙(がんぴし)などにしみ込ませてカーボンペーパーが作られました。書類作成などで用紙の間に挟んで写しを得る複写に用いました。いつごろから日本でカーボンペーパーが使われ出したのか、はっきりしたことは分かりませんが、明治時代の後半には輸入品のカーボン紙が使われていたとのとです。当時、カーボン紙「carbon paper」の誤訳でこれを「炭酸紙」とか「炭素紙」と呼ばれていました。
「炭酸紙」の国産品は、明治の終わりころにススを油で溶いて和紙に塗りつけたものが登場し、大正時代初期には塗液にワックスを混合して、汚れやにじみを押さえた炭酸紙が現れて、官庁向けなどに出荷されていました。さらに大正末期には、現在のような洋紙をベースとしたものが使われるようになり、「カーボン紙」の名称も一般化してきましたが、大きな需要先であった鉄道の貨物作業の受け渡し事務用のものはどうしても「和紙ベース」でなければいけないということで、昭和25年頃まではこれも使われていました。
現在では、コピー機の普及によって生産量は減っているものの、公用文書や見積書・貿易ドキュメントなどに、カーボンペーパーは根強い需要があるようです(ホームページゼネラル株式会社:カーボンのミニ歴史 カーボン紙の歴史-ゼネラルサプライ株式会社から引用)。
(2)裏カーボン原紙
カーボンインクは顔料のカーボンブラックを使用しますが、裏カーボン原紙は複写のためにカーボンインクを裏面に塗布した原紙です。ワックスタイプのカーボンインクを全面またはスポット状にグラビアコーター、あるいは印刷で裏面に塗布し、事務用伝票として用いられます。複写伝票には長い間、カーボン紙を紙と紙の間にはさんで使用していましたが、1952年にカーボン紙を挿入する手間を省き、複写枚数を増やすために裏面全体にカーボンを塗布したクリーンカーボン(裏カーボン)ができました。そして1954年に複写必要スペースの裏面のみにカーボンをスポット印刷するスポットカーボン伝票の時代を迎えました。同時に、専用の裏カーボン原紙も開発されカーボンインキの定着が良く、裏抜けしない、不透明性の高い製品が生み出されてきました。しかし、1960年代にはノーカーボン紙の出現により使用は減少し始めました。1980年代には宅配便の伝票に使用され再び増加傾向が見られましたが、前記のノーカーボン紙の増加に伴い、その需要は大きく減少してきています。標準坪量は41g/m2ですが、必要に応じて50g/m2もあります。
(3)その他複写原紙
クリーンカーボンペーパーなどの複写用原紙が含まれます。クリーンカーボンペーパーは、裏カーボン紙のカーボンインキ層の上に白色被覆層を作り、カーボンによる汚れを防止したカーボン紙で事務用伝票に使われます。
2.感光紙用紙
ジアゾ感光紙(青写真)の原紙で、原紙にジアゾ感光液を塗布し、感光紙が作られます。ジアゾ化合物は光によって分解する原理を応用しているもので、写真印画紙と同様、ジアゾ感光紙に複写しようとする原稿を重ね、光を当てると光が遮られる原稿の画像部分はジアゾ化合物が残ります。これを現像液に漬けると化学反応してアゾ染料が生じ発色し、文字や図形などの画像部が複写され表れてくるわけです。
ジアゾ感光紙は、もともと染料化学に強いドイツで発明されたものであり、わが国で製造されたのは、1927(昭和2)年のことです。片面が薬品処理された淡黄色の紙で、感光防止のため、内側に黒いポリエチレンフィルムを貼った袋に入れられ、販売されていました。かつては複写紙の代表でしたが、単票でかつ薄い原稿しか複写できないこと、保存が難しいこと、臭気があることなどから需要は減少し、現在では普通紙コピー(PPC用紙)が主流となっています。しかし、かなり大きなものまで複写できることから、今でも工業用製図・図面などに欠かせないものとなっています。
感光紙の原紙は、上質紙ベースで感光液が均一に塗工できるように地合、表面性が良く、強サイズ性が要求されますが、写真感光反応に悪影響を与えないように鉄などの不純物を含まないことが重要です。